はじめに
はせがわこどもクリニックでは、小児科・児童精神科・精神科としての専門性を活かし、教育・福祉・医療・行政など、さまざまな分野の機関からご依頼をいただき、講義・講演・研修・スーパーバイズなど幅広い形で対応しています。
お子さんや保護者の方のためになると判断したものについては、できる限り積極的にお引き受けしており、現場のニーズに即した支援を大切にしています。
また、専門家として「すべての支援者に知っておいてもらいたい」と考える内容については、セミナーを企画して自ら発信する形でもお伝えしています。
「子どもと関わるすべての現場のレベルアップ」を目指し、実践に役立つ知識と視点を、さまざまな立場の支援者の方々へ届けていくことを大切にしています。
主催セミナー情報
こども支援の現場力UPセミナー
~こどもと関わるすべての機関向け オンラインセミナー~
本セミナーの特長「医療と法律の専門性を、現場で活かせる形で学ぶ」
本セミナーでは、教科書的な知識の解説にとどまらず、日々の支援現場で実際の現場で起こる具体的なケースをもとに、その子の特性について「どこに着目して見立てを立てるか」「どのような判断や対応が適切か」といったより実践的な視点を重視しています。
ケース検討では、その場限りの問題解決のみではなく、
- 長期的にどのような経過をたどる可能性があるのかという「見通し」
- 成育歴や関わりの積み重ねも踏まえた「アセスメントの視点」
を軸に支援の方向性を整理していきます。
例えば、年長児で同じような行動や困り感がみられる場合でも、幼少期からの経過によって評価や支援の方向性は大きく異なるため、幼少期のどのような情報を把握すべきかなどについても具体的に扱います。
さらに、本人だけでなく保護者の特性や心理的背景も含めた包括的な支援の組み立て方についても触れ、現場で「次の支援の一手」を選ぶ際の具体的な視点を学んでいただける内容となっています。
また、法律に関する視点は、日々の支援現場では後回しにされがちですがトラブルを未然に防ぎ、安心して支援をおこなうための「土台」として非常に重要です。
本セミナーでは、単なる制度の枠組みの解説だけでなく、支援現場で実際に起こりうるトラブルをもとに、
- 保護者とやり取りする際に法的に問題のない対応を行うには何が必要か
- 施設として法的にしてはいけないことやしないといけないことは何か
といった視点から、リスク予防や体制整備について具体的に考えていきます。
医療と法律、それぞれの専門的な視点を土台として、管理者・現場支援者それぞれの立場に沿って学べる構成となっており、参加後すぐに現場で活用できる「アセスメント力」「対応力」などを養うことができます。
セミナー企画の背景「現場からの生の声と課題の解決へ」
保育園、学校、塾、習い事など、日々たくさんのお子さんと関わっている先生や、放課後等デイサービス、児童発達支援、児童養護施設、医療機関など専門性が期待される現場であっても、発達特性や法律への理解が十分に浸透していないため様々問題が起こってしまっているという課題を、日々の診療や講演、事例検討会を通じて強く感じています。
「どこに着目して見立てを立てればよいか分からない」
「対応に自信が無く、支援するはずが保護者と一緒に悩むだけになってしまう」
「本では学んだけど、実際の場面でどう応用すればいいか分からなかった」
「薬物療法がどのような基準で行われるのかが分からず、今後の支援の見通しが立てられない」
「保護者対応に不安があり、トラブルが起きた際に誰に相談すればいいか分からない」
「保護者とのトラブルで訴訟に発展したが、どのように対応していれば防げたのか」
「現在施設として行っている対応が法的に問題ないか自信が無く、職員間での方針の統一も難しい」
こうした声から見えてくるのは、教科書的な知識はあっても、実際の現場では活かされていないという現状です。
その結果として、適切でない対応や判断により保護者との関係性が崩れてしまい、トラブルや訴訟に発展してまうケースも少なくありません。
そして熱意をもって関わっていた支援者ほど疲弊してしまい、休職や離職に至ってしまうことも数多く見てきました。
支援の質を高め、現場で支援する方々が安心して判断して対応できるようにするには、医療、法律のそれぞれの専門性に基づいた「正しい判断」と「適切な対応」について具体的なケースを通して継続的に学ぶ場が必要だと考えています。
しかし、現状ではそのような学びの機会は非常に限られており、中には「治る」「解決する」「全てが分かる」といった誤解を生むような表現をしているものすら見受けられます。
こうした背景のもと、現場の最善線で活動する医療、法律それぞれの専門家が連携し、ケースをもとにした実践的な学びを提供するセミナーを立ち上げることに至りました。
講師紹介
長谷川 雅文(はせがわこどもクリニック 院長)
小児科、児童精神科、精神科を専門的に診療しており、年間のべ10000人以上のこどもやその保護者を診察するこころとからだの専門医。
また、複数の機関での嘱託医を務め、支援機関での講演や講義も多数行っている。
資格
- 医師(小児科・児童精神科・精神科)
- 日本小児科学会専門医
- 精神保健指定医
- 子どものこころ専門医/指導医
- 子どものこころ相談医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 日本医師会認定産業医 など
中川 源力(Kollectプラス法律事務所 代表)

医療や福祉・教育分野における法的課題に精通し、多数の子ども教育関連施設が顧問先としている。
資格
- 弁護士
- 税理士
- 宅地建物取引士
対象
- 児童福祉センター
- グループホーム
- 児童養護施設
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 保育園
- 幼稚園
- 習い事
- 医療機関
など、こどもに関わる全ての支援機関を対象としています。
開催概要
- 第1回(管理者向け)管理者スキルをUP!保護者トラブルとさようなら
:2025年7月27日(日)14:00〜16:00
ZOOM配信 アーカイブ視聴あり(〜8月26日)
こどもの特性を把握して適切な対応を指導することはもちろん、
保護者の特性や法律上の事も踏まえて支援の枠を決定するなど
管理者以上の方の視点を中心とした内容となっています。
適切な対応を行うことによってトラブルを未然に防ぐことができるようになり、
さらにスタッフが成長しやすく、疲弊しにくい職場環境を実現することにつながります。
参加費:第1回(管理者向け):8,000円(税込・アーカイブ含)- 第2回(現場スタッフ向け)現場力をUP!安心と信頼を得るには?
:2025年8月31日(日)14:00〜16:00
ZOOM配信 アーカイブ視聴あり(〜9月30日)
現場で起こる出来事についての見立ての立て方や具体的な対応についてなど、
現場スタッフの視点を中心とした内容となっています。
より幅広く見立てが立てられるようになり、
してはいけない対応やその理由を知ることによって、
経験したことが無い場面に対しても対応力が向上し、
保護者からの信頼獲得につながります。
参加費:第2回(現場スタッフ向け):6,000円(税込・アーカイブ含)
セット受講12,000円(税込・2,000円割引・アーカイブ含)
セミナー受講施設・参加者
※セミナー受講の情報掲載は、掲載希望を承った施設様・参加者様のみとなっております。
- 施設名:特定非営利活動法人Reframe 様
参加セミナー歴
2025年7月27日 こども支援の現場力UPセミナー シリーズ①Vol.1 第1回【管理者向け】参加人数 1名
2025年8月31日 こども支援の現場力UPセミナー シリーズ①Vol.1 第2回【現場スタッフ向け】 参加人数 1名
- 施設名:株式会社みのりの森 様
参加セミナー歴
2025年7月27日 こども支援の現場力UPセミナー シリーズ①Vol.1 第1回【管理者向け】参加人数 1名
2025年8月31日 こども支援の現場力UPセミナー シリーズ①Vol.1 第2回【現場スタッフ向け】 参加人数 1名
- 施設名:訪問看護ステーション デューン二条 様
参加セミナー歴
2025年7月27日 こども支援の現場力UPセミナー シリーズ① Vol.1 第1回【管理者向け】参加人数/参加者 1名/秋山僚汰様
申込方法
Peatixより受付(Googleアカウントで登録可能)
よくある質問
- どんな立場の人でも参加できますか?
→ 学生・保護者含めどなたでも参加可能ですが、現場の支援者の視点を中心とした内容となりますので予めご了承ください。 - アーカイブ配信はありますか?
→ 開催日より1ヵ月間視聴可能です。リアルタイムで視聴ができなくてもお申込みいただけます。 - 認定証は発行されますか?
→ 現段階では認定証や資格証の発行の予定はございません。参加された施設様でご希望がある場合は、受講者人数も含めて「はせがわこどもクリニックWEBサイト内」で掲載させていただきます。
※申し込み時に入力していただいた施設名を掲示させていただきます
※所属施設が無い場合は<個人>として掲載させていただきます
注意点
- お申込後の参加者様都合のキャンセルの場合は、返金対応は致しかねますのでご了承ください。
- 講演内容の録画、録音はご遠慮ください
お問い合わせ
問い合わせフォームへご連絡ください(次回セミナーの予定が公開されている期間のみ解放しています)
※返答まで数日程度お待ちいただく事がございますがご了承下さい
最後に
このセミナーは児童精神科医として日々の診療を行う中で、弁護士として日々の相談を受ける中で、支援者の方に知っておいてほしいことについての専門家としての生の声が詰まっています。
支援の現場では「こうすれば必ず上手くいく」という都合のいいものはあまりなく、現在抱えている問題についてきちんと評価して見立てを立てることによって適切な支援につながる正しい選択を繰り返すことが大切です。
診察室の中で、本人や保護者の方に伝えることはできますが限られた診察時間の中でうまくいかずに悩んでいる支援者の方にまで伝えることは難しいです。
少しでも多くの機関にこのセミナーの存在を知っていただいてよりよい支援の現場を作っていきたいと考えています。
周りにこども支援の現場で活躍する方がおられましたら是非当セミナーについて共有していただければ幸いです。
活動紹介
外部での講義・講演
- 2025年
メディア掲載・連載・インタビュー
- 2023年
-
クルールきょうと7・8月号「子育ての悩みについてのアンケート・クリニック紹介」
クルールきょうと9・10月号「インフルエンザワクチン・ショートケアプログラム~あかり~」
クルールきょうと11・12月号「冬に流行する代表的な感染症・児童精神科外来の初診の流れ」
- 2024年
-
クルールきょうと1・2月号「産後ママ外来」
クルールきょうと3・4月号「産前産後ケア・産後ママ外来の具体的な受診例」
クルールきょうと5・6月号「オンライン相談室~いこい~」
クルールきょうと7・8月号「読者アンケートからいただいたママのお悩みとその解決先」
クルールきょうと9・10月号「当院で行っている診療や診療を超えての親子へのサポート体制」
クルールきょうと11・12月号「冬に流行する代表的な感染症・児童精神科外来の初診の流れ」
- 2025年
-
看護師転職支援サービス「レバウェル看護」コラム掲載
コラム記事はこちら(外部リンク)「GLOW6月号 全国のおすすめドクター&クリニック46」掲載
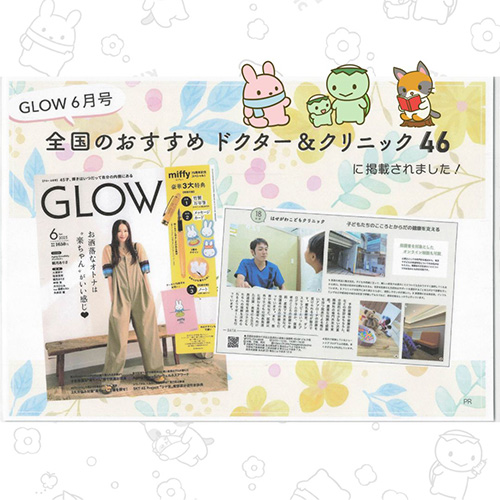
クルールきょうと1・2月号「通院の必要性」
クルールきょうと3・4月号「産前・産後ママ外来」
クルールきょうと5・6月号「この時期に気を付けたいこと」
クルールきょうと7・8月号「こどもと関わるすべての現場がよりよくなるために」
現在進行中・調整中のプロジェクトや連携機関など
- 京都市はぐくみ室や療育機関と連携した健診フォローシステムの構築
- 産婦人科機関と連携した出産前からのハイリスク妊婦支援
- 保育園・幼稚園の園医健診業務
- 東大阪市こども家庭センター嘱託医業務(月1回 医療相談 適宜支援会議参加)
- 京あんしんこども館嘱託医業務(各月 医療相談)
など
医療 × ダンスの取り組み
院内のショートケア・プログラムでダンスセラピーの導入
Medibase(医療系ダンスコミュニティ)主催
医療従事者および医療系学生のみで構成されたダンスコミュニティで、メンバー数は120名を超えます。
ダンスを通じて、世代を超えたメンバー同士の交流・知識の共有や啓発・チームビルディングを目的に活動しています。
関西圏を中心に、学園祭や地域イベント・WS(ワークショップ)などへの出演・主催を通じて、「医療×ダンス」という新しいつながりの形を広げています。
また医療・ダンスと親和性の高い企業様との連携による、さまざまな取り組みも展開しています。
2024〜2025年 活動実績(一部を抜粋)
- 2024年
-
2月:西日本医療系大学ダンスイベント Drive 参加出演
3月:奈良県立医科大学ダンス部主催 Smiles 参加出演
4月:兵庫県立医科大学ダンス部主催 FUNK 参加出演
7月:大阪医科薬科大学ダンス部主催 Shoooot参加出演
医療系多ジャンルWS Medicamp Vol.1 主催
近畿大学医学部ダンス部主催 SuperRote参加出演
9月:世界トッププロダンサーHilty &Bosch ZIN主催 ZONE Osaka Vol.2 参加出演
10月:大阪医科薬科大学学園祭 参加出演
和歌山県立医科大学学園祭(夜祭)参加出演
関西医科大学学園祭 参加出演
11月:近畿大学医学部学園祭( 金剛祭) 参加出演
12月:医療系多ジャンルWS Medicamp Vol.2 主催
医療系ショーケースイベントMediclum Vol.2 主催
- 2025年
-
2月:西日本医療系大学ダンスイベント Drive 参加出演
4月:名古屋大学医学部ダンス部(Doppin) WS企画
兵庫県立医科大学ダンス部主催 FUNK 参加出演
5月:和歌山県立医科大学ダンス部(Intact)WS企画
6月:医療系多ジャンルWS Medicamp Vol.3 主催
7月:大阪医科薬科大学ダンス部主催 Shoooot参加出演
近畿大学医学部ダンス部主催 SuperRote参加出演
LockFit(高齢者向け健康ダンス)
LockFit(ロックフィット) は、理学療法士・プロダンサー・精神科医の共同開発により生まれた、Lock Dance(ロックダンス)の要素を最大限に活かした、エビデンスに基づく高齢者向けの健康ダンスプログラムです。
運動刺激、音楽のリズム、社会的交流を組み合わせることで、脳機能の活性化や認知機能の維持を促すほか、自己肯定感・主観的幸福感の向上にもつながることを目的としています。
「楽しく、安全に、継続的に取り組める健康体操」として、誰もが音楽に親しみながら自然に笑顔になれる構成を目指したプログラムとなっています。
- 活動実績(一部を抜粋)
-
- 大阪府高石市 社会福祉協議会と連携し、地域の高齢者が集まる拠点で継続的に実施中
- 大阪市福島区 社会福祉協議会・地域包括支援センター関係者に向けてプレゼンテーション、今後定期開催に向けて準備中
- 大阪府豊中市 高齢者施設にて実施
- 高校バスケ部でのリズムトレーニングとして導入実績
- ビジネスコンテスト「たかじんフェロー」優勝(地域課題解決型の社会貢献ビジネスとして評価)
地域イベントでの健康啓発活動
など




